Umbrella Company / The Fader Control
導入事例(ユーザー活用例)
株式会社Nirvana
レコーディングエンジニア 森田 良紀 様
www.studioforesta.com
SOUND DESIGNER 2016年2月号に掲載された
The Fader Controlの製品レビューでは、ユーザーでもあるレコーディングエンジニアの森田良紀さんにご協力いただきました。
スライドフェーダーのボリュームコントローラーとしては便利な機能を多く搭載しており、トラッキング時のボリュームコントロールをはじめ様々な用途に応用できる製品で、限定発売当時に導入していただいた森田さんも、ボーカルレコーディングをはじめ、DSDの収録やUstreamやニコニコ生放送などのネット配信の現場の重要な役割として、機能をフルに活かしてお使いいただいています。
今回、SOUND DESIGNERのレビューでは書ききれなかったThe Fader Controlの活用法を中心に、改めてご紹介と評価をしていただきました。

★INPUT MODE活用例
INPUT MODE:マイクプリアンプからの信号やラインレベルの信号を入力し、主に録音時のレベリングに最適な機能構成となります。モノラル/ステレオの切替や音量スケールの切替も可能です。
①ボーカルレコーディング時のレベルコントロール
ボーカル録音時のダイナミクスのコントロール(コンプレッサーの掛かり具合の調整)に使います。
ボーカリストによっては歌唱時の音量がAメロやBメロは小さく、サビでは大きくなるような人もいます。
バックのオケも同じ傾向であれば良いのですが、オケがある程度の音量で常に鳴っている場合、時にサビの音量にマイクのゲインを合わせてしまうとAメロやBメロが小さくなってしまい聞こえづらくなってしまう事があります。かといってその音量差をコンプレッサーで整えてしまうと、サビでは極端にコンプレッションがかかってしまい、サビなのに声が抜けてこない、なんて事にもなりかねません。
そんな時、今まで可能な場合はAメロBメロとサビでマイクプリのゲインを変えたり、Urei 1176のインプットレベルで調整したりとしていましたが、マイクプリではゲインステップが細かい機種で1dBステップ、大きいと5dBステップなんてこともある為、そんなに上げたくない場合には適しませんでした。1176のインプットの場合もロータリーポットのため微妙な音量調整が難しい上に、状態が悪いとガリノイズなども発生して使い物にならないこともありました。TUBE-TECH CL1Bも良く使用しますが、この場合はインプットボリュームは無い為、サビに合わせたスレッショルドで後はアウトプットボリュームで調整するしかありませんでした。

このようなレベルの調整にサビのレベルでマイクプリを設定し、その後にThe Fader Controlを使うことで、ガリノイズも全く起きずに非常にスムースなコントロールを行うことができます。またモノラルの素材に使う場合には、レベルコントロールした音声を出力できるだけでなく、もう片方の出力からフェーダーを介さない固定レベルの信号も出力できるので、そのまま録音しておけばコンプレッションもかかっていない素の音のバックアップも同時に録っておくことができます。意外と音声をスプリットする機材も高音質な物は少ない為あると便利な機能です。
SSLやNEVEなどの大型のコンソールであれば当たり前にやっていたこのような事も、Pro ToolsなどのDAW録音になってからは中々容易には出来なかった為、このようなフェーダーは本当に重宝しています。
また、本体が小さい為、色々なスタジオに移動しての作業の場合でも気楽に持ち運べるのも利点の一つです。
②2Mixのレベルコントロール
・特にDSD音声を扱う場合に、レコーダー内でPCM音声のようなフェード処理は基本的には行えないため、録音する段階での適切なフェーダー操作が必要でした。今まではその為に高価でサイズも大きなミキサー卓を使用するしか無かったのですが、アナログ音声のまま処理の出来るThe Fader Controlを使うことで小型で場所もとらず、位相の狂いの無い適格なレベルコントロールが行えるので助かっています。
またDSDレコーダー2台を使ってのピンポン録音する場合のレベル調整にも最適です。
③配信用のマスターフェーダー
・Ustreamやニコニコ生放送、YouTube Liveなどのライブ配信での番組制作では、生放送ならではのとっさのレベル調整が必要な事が多い為、フェーダーの質感、音質として信頼の出来るマスターフェーダーとしてThe Fader Controlを使っています。視覚的にもフェーダーが上がっていればOnAir、下がっていればOffAirと分かりやすいのもバタバタする現場では助かります。

★OUTPUT MODE活用例
OUTPUT MODE:主にDAWシステムのモニター・コントローラーとしてお使いいただける機能構成となります。
①ライブ収録時のモニターコントローラー
・仮設で組んだスピーカーでモニターする際のボリュームコントローラーとして使っています。ディマーやミュートの機能も付いているので、スタジオで作業している時と同じ感覚で使えます。またボタン一つの切替で高品質なヘッドホンアンプとしても使えるので、別途ヘッドフォンアンプを用意すること無く、モニタークオリティでの正確な判断が出来ます。
※The Fader Controlを2台所有しているので、一台はINPUT MODEでレベルコントロールに、もう一台はモニターコントローラーとして使用する事も多い。

★仕様、機能について
①ハイレゾ素材にも対応した高品質なサウンド:
曲のメインとなるボーカル録音時のレベルコントロールや2Mixのマスターフェーダーとしても十分に対応できる音質で、快適に作業が行えます。またヘッドホンアンプとしても高級ヘッドホンアンプと変わらない音質で、最近の高級ヘッドフォンなどでも駆動出来るドライブ能力もあり、非常に扱いやすいです。
②ユニティーレベル・インジケーター:
ユニティーレベルのフェーダー位置でLEDが点灯するので、神経質に目盛やメーター上で合わさなくても素早く0レベルが設定できて非常に便利です。また視覚的にも判断し易い為、バタバタしている現場などでは助かります。

③高精度なボリュームコントロール:
ステレオのボリュームコントロールを行う場合、フェーダーの位置をかなり下げてもLRのレベル誤差が起こらず、ガリノイズも全く起きずに使えるので、ステレオ素材のマスターにも信頼して使えます。
④快適な操作感と動作:
高価なコンソールのアナログフェーダーを操作しているような快適な操作感と、スムーズなレべルコントロールが行えます。オプションでSSLやNEVEのコンソールで採用されているP&G社製のフェーダーも選べます。
⑤安定動作を生み出す電源:
The Fader Controlの電源は、スイッチング式のACアダプタや内部電源レギュレーターを採用していて、かなり不安定な電源環境でも安定した動作ができるように作られています。屋外やライブ会場などの電源環境の良くない現場でもハムノイズなどの影響を受けずに、会場の電圧が低下している場合でも、安定した動作をしています。
また、オプションでACジャックからプラグが抜けないように、ロックタイプのプラグを選べるところはいいですね。外録で機材の設置が不安定な環境でも安心して使えます。

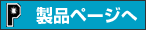





 このようなレベルの調整にサビのレベルでマイクプリを設定し、その後にThe Fader Controlを使うことで、ガリノイズも全く起きずに非常にスムースなコントロールを行うことができます。またモノラルの素材に使う場合には、レベルコントロールした音声を出力できるだけでなく、もう片方の出力からフェーダーを介さない固定レベルの信号も出力できるので、そのまま録音しておけばコンプレッションもかかっていない素の音のバックアップも同時に録っておくことができます。意外と音声をスプリットする機材も高音質な物は少ない為あると便利な機能です。
SSLやNEVEなどの大型のコンソールであれば当たり前にやっていたこのような事も、Pro ToolsなどのDAW録音になってからは中々容易には出来なかった為、このようなフェーダーは本当に重宝しています。
また、本体が小さい為、色々なスタジオに移動しての作業の場合でも気楽に持ち運べるのも利点の一つです。
このようなレベルの調整にサビのレベルでマイクプリを設定し、その後にThe Fader Controlを使うことで、ガリノイズも全く起きずに非常にスムースなコントロールを行うことができます。またモノラルの素材に使う場合には、レベルコントロールした音声を出力できるだけでなく、もう片方の出力からフェーダーを介さない固定レベルの信号も出力できるので、そのまま録音しておけばコンプレッションもかかっていない素の音のバックアップも同時に録っておくことができます。意外と音声をスプリットする機材も高音質な物は少ない為あると便利な機能です。
SSLやNEVEなどの大型のコンソールであれば当たり前にやっていたこのような事も、Pro ToolsなどのDAW録音になってからは中々容易には出来なかった為、このようなフェーダーは本当に重宝しています。
また、本体が小さい為、色々なスタジオに移動しての作業の場合でも気楽に持ち運べるのも利点の一つです。
