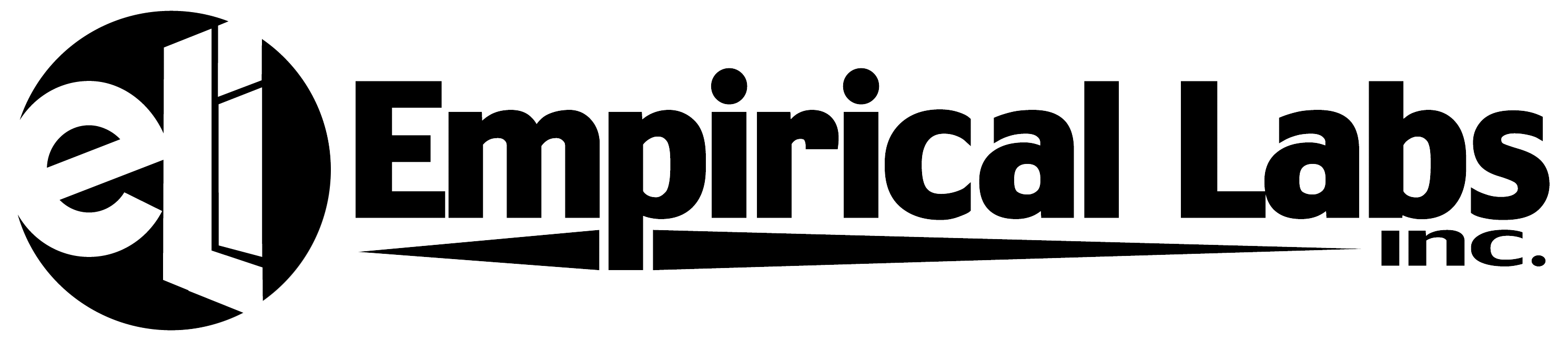ディストレッサーを創造したモダーンデザインの代表的ブランド
Empirical Labsはデジタルレコーディングに、失なわれた<宝石>を連れ戻しました。本物のアナログ回路を自在にスイッチングする事でプラグインなどのアナログモデリングでは決して到達できない<本物のアナログ質感>を原音に加えることができます。
Empirical Labsの製品は二次倍音(ハーモニクス)や三次倍音といったトランスフォーマー、真空管、アナログテープなどが持つ独特のアナログ質感を自由自在にコントロールする事が可能です。これはアナログテープ時代の質感が失われつつあるデジタルレコーディング全盛の現代において、Empirical Labs製品がスタジオ機器の標準となっている一つの理由です。
本物のアナログ質感、ビンテージの美しさは、本物のアナログ回路でしか表現できない。パレットの絵具のように <アナログ> を自在にミックスするワールドスタンダード。
ALL PRODUCTS
ディストレッサー w/オプション
Digitally Controlled Analog Knee Compression(w/Option)
ディストレッサー
Digitally Controlled Analog Knee Compression
ステレオ・オプティマイザー
Full Analog Tape Simulator & Opimizer
マイクプリ+ディストレッサー
Mic pre amp + Distressor
ディエッサー(API500)
Multi function Dynamic Filter
コンプレッサー/EQ(API500)
EQ with Comp / Saturator